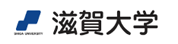経済学部の学生がラオス国立大学で交流活動を行いました。
 9月19日~29日、経済学部生19名がラオスを訪問しました。このプロジェクトは、学生が自ら企画し、現地の人々との交流を通じて、経済発展や国際協力の本質を自分の目で見て考えることを目的としています。限られた期間ではありましたが、数多くの発見や困難を経験しました。
9月19日~29日、経済学部生19名がラオスを訪問しました。このプロジェクトは、学生が自ら企画し、現地の人々との交流を通じて、経済発展や国際協力の本質を自分の目で見て考えることを目的としています。限られた期間ではありましたが、数多くの発見や困難を経験しました。
プロジェクトの初めには、本ゼミに所属するラオス出身学生の実家を訪問しました。そこでは、大切な人の健康と幸せを願う儀式を体験させていただき、多くのラオス料理を振る舞っていただきました。親戚の方々と一緒にラオスの遊びを楽しむなかで、家庭のあたたかさや豊かな文化に触れることができました。家族の皆さんと過ごした時間は、ラオスの文化を肌で感じるかけがえのない経験となりました。
 ラオス国立大学での2日間では、ラオスの学生や技能実習生を目指す方々と交流をしました。当初の予定とは異なる参加者構成により、コミュニケーションに苦労する場面もありましたが、お互いに工夫しながら言語の壁を乗り越えました。「幸せにとって最も大事なものは何か」というテーマで議論を行い、昼食時にはお互いに料理を作って食文化の交流を行いました。これらの経験から、異文化交流においては言葉よりも「相手を理解しようとする姿勢」が大切であると実感することができました。
ラオス国立大学での2日間では、ラオスの学生や技能実習生を目指す方々と交流をしました。当初の予定とは異なる参加者構成により、コミュニケーションに苦労する場面もありましたが、お互いに工夫しながら言語の壁を乗り越えました。「幸せにとって最も大事なものは何か」というテーマで議論を行い、昼食時にはお互いに料理を作って食文化の交流を行いました。これらの経験から、異文化交流においては言葉よりも「相手を理解しようとする姿勢」が大切であると実感することができました。

農村部、都市部それぞれの小学校を訪問しました。そこでは、石鹸を使った手洗いを音楽とダンスを交えて楽しく教えたほか、折り紙やクイズ、ラオスの子どもたちから教わった遊び、長縄跳びやサッカーなどを通じて交流しました。子供達の笑顔と、純粋に楽しむ姿は私たちにとって忘れられない光景になりました。また、滋賀大学近隣の小学生から寄付していただいた支援物資や、大学生・大学関係者の方々や地域住民の方々からの募金により購入した物資をラオスの小学生に届けることができました。さらに「豊かさとは何か」をテーマに、日本・ラオス双方の児童が描いた絵を交換し、日本の小学生から寄せられた質問をラオスの子どもたちが答えるという交流も行いました。今後はその回答をもとに日本の小学校を再訪し、ラオスの現状を伝える予定です。こうした往復型の交流が日本の児童にとって国際社会への関心を持つきっかけになることを願っています。
 今回のラオスプロジェクトでは、文化・教育・経済などの現地の姿を多面的に自分の目で見ることができました。また、人々との交流を通して経済的な指標や「貧困」「格差」などのような言葉だけでは表現しきれない現実を、学生一人ひとりが身をもって感じることができました。また、それらを通じて「支援とは何か」「支援をするなら、どのような支援が必要か」という点について深く考える機会を得ました。
今回のラオスプロジェクトでは、文化・教育・経済などの現地の姿を多面的に自分の目で見ることができました。また、人々との交流を通して経済的な指標や「貧困」「格差」などのような言葉だけでは表現しきれない現実を、学生一人ひとりが身をもって感じることができました。また、それらを通じて「支援とは何か」「支援をするなら、どのような支援が必要か」という点について深く考える機会を得ました。