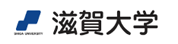経済学部・府内教授の論文がGames and Economic Behaviorに掲載されました。
経済学部・府内直樹教授 の論文がGames and Economic Behavior(ゲーム理論や理論経済学の分野で評価の高い、 Social Science Citation Indexの指標に含まれている専門誌)に掲載されました。
論文の概要
これまでのゲーム理論における学習理論では、すべての人が同様に学習する「同質的な学習者」が仮定されてきました。しかし、実際の社会では、経験を通じて行動を変える人もいれば、変えない人も存在します。本研究では、このような「学習者」と「非学習者」が共存する社会において、慣習がどのように形成され、安定していくのかを探究しました。
たとえば、「歩行者が右側を歩くか左側を歩くか」といった身近な意思決定の場面を考えてみましょう。右側通行が社会の慣習として定着しているのは、経済学でいう「ナッシュ均衡」が成立している状態です。本研究では、このような意思決定の場面において、学習者と、特定の慣習(たとえば右側通行)に従う非学習者が混在しているとき、社会全体の行動(慣習)がどのように変化していくのかを分析しました。
その結果、学習者同士の交流頻度に「閾値(しきいち)」が存在することが明らかになりました。学習者同士の交流頻度が閾値を下回り、学習者が非学習者と頻繁に交流する場合、学習者は非学習者の行動(既存の慣習)に自然と同調する傾向があります。一方で、交流頻度が閾値を上回る場合には、学習者が別の慣習(たとえば左側通行)に従う可能性が生じます。
この閾値は、意思決定における「利得構造」、すなわち行動の結果としてどの程度の利益や損失が生じるかによって変化します。特に、慣習から逸脱した際の損失(たとえば歩行者同士の衝突など)が小さいほど、同じ交流頻度でも既存の慣習が維持されにくくなり、社会的な混乱が生じやすくなることが示されました。
本研究の重要な点は、人々が必ずしも高度に合理的でなくても、経験から学ぶだけで社会的な慣習が自然に形成されることを示した点にあります。さらに、社会的な衝突を回避するためには、学習者と非学習者の交流頻度が重要な役割を果たすことも明らかになりました。
※本研究は、科研費(23K22098)および滋賀大学経済経営研究所(受付No. 2205)からの研究支援を受けた成果です。また、滋賀大学とElsevierの契約に基づき、本研究論文はオープンアクセスとして公開されており、無料で閲覧・ダウンロードが可能となっています。