- 日 時:2025年11月14日(金)16:10〜17:30
- 表 題:南アジアの多言語状況と異文化コミュニケーションの現状と課題
- 発表者:レザウル・カリム・フォキル(バングラデシュ・ダッカ大学,神戸学院大学客員教授)
- 開催場所:士魂商才館セミナー室Ⅰ
- 開催様式:対面&WEB
- 講演言語:日本語(一部英語有)
- 司会:野瀬昌彦(本学経済学部教授)
対面で参加をご希望の方は会場へ直接お越し下さい。
講演要旨
南アジアでは、教育では英語、宗教では古典語、行政では国語と地域言語が使い分けられるという、きわめて複雑で重層的な言語構造が見られます。言語は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、社会的身分や民族的アイデンティティを示す重要な指標でもあります。
このような多言語環境の中で、人々は日常的に巧みに言語を切り替えながら生活していますが、同時にその言語選択が社会的な対立や不平等の要因となることもあります。本講演では、南アジアの言語使用の実態を通して、言語と社会、文化、そして政治の関係を考察します。また、異文化コミュニケーションの観点から、多様な言語の価値を認め合い、相互理解を促進する新たな共生の枠組みについて提案します。
講演報告
インド,バングラデシュ,パキスタン,ブータン,ネパール,アフガニスタン,スリランカなどの地域は南アジアと呼ばれる地域であり,言語学的に印欧語,シナ=チベット,オーストロアジアなどの語族が入り乱れる,多言語の共存する地域である.
今回、講演をお願いしたのは2025年の春学期にも滋賀大にて講演いただいた,バングラデシュのダッカ大学の教授であるレザウル先生で、彼はダッカ大学の日本語学科の主任であり、バングラデシュにおける日本語教育を牽引する人物である。講演では、南アジア地域の多言語状況に関して,異文化間コミュニケーションの点に特に着目して,日本語でお話しいただいた。
南アジア地域では,国も違えば,言語も,宗教も様々で,教育では英語,宗教では古典語(サンスクリットなど),行政では公用語と地域言語が使い分けられるという,きわめて複雑で重層的な言語構造が見られる.そのため,言語は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず,社会的身分や民族的アイデンティティを示す重要な指標でもある.このような多言語環境の中で,南アジアの人々は日常的に巧みに言語を切り替えながら生活し,同時にその言語選択が社会的な対立や不平等の要因となることもある.
本講演は,滋賀大の授業科目である「異文化間コミュニケーション論」の発展形で,専門的すぎる内容もあったが,多くの学生が聴講し,南アジアの地域の言語や文化の学習機会となった.
(文責 経済学部教授 野瀬昌彦)

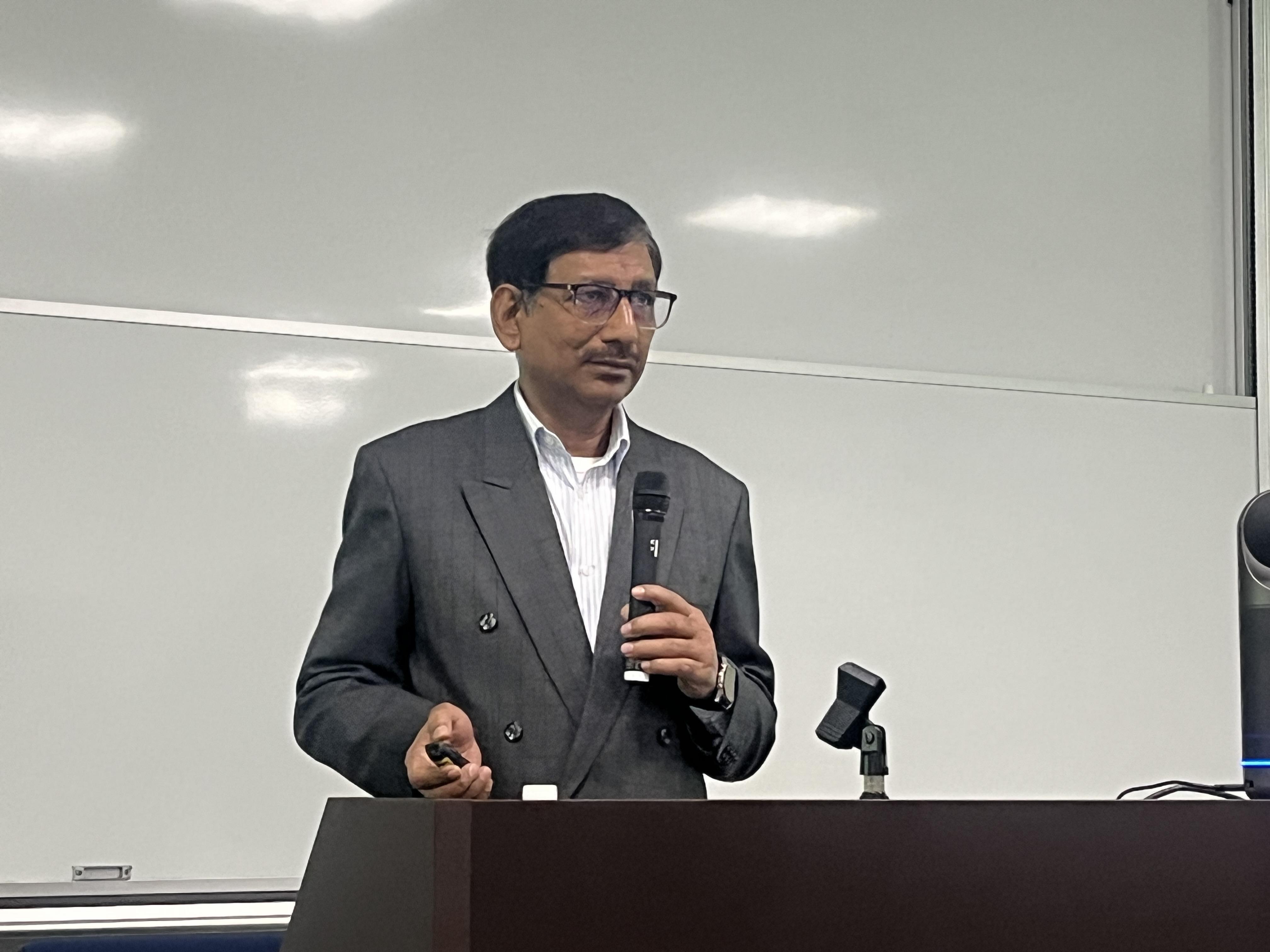
本ページに関するお問い合わせは
滋賀大学経済経営研究所
TEL : 0749-27-1047 /FAX : 0749-27-1397
E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp ★(at)を@に変更して送信してください。






