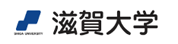向組織的非倫理的行動の生起メカニズムの研究
本研究の目的は、近年の組織行動論で注目される新しいタイプの従業員不正、すなわち経営者や経営幹部によって命令されたわけではない、従業員自身の「組織にとって良かれ」という判断に基づいて行われる不正行為の発生メカニズムを明らかにすることである。このような不正行為は海外研究において非倫理的向組織的行動 (Unethical Pro-Organizational Behavior:UPB) と呼ばれている。
本研究の学術的特色は、以下の2点であった。 1つ目の特色は、単にUPBを抑制する要因を検討するのではなく、他の向組織的行動と比較しながら、UPBのみを抑制する要因を検討する点である。本研究が注目する不正行為は、従業員自身の「組織にとって良かれ」という判断に基づいて行われている。すなわち、不正行為の動機には組織に対する貢献意欲が含まれている。したがって、単に従業員のUPBを抑制する要因を明らかにするだけでは、同時に当人の組織に対する貢献意欲も低下させてしまっている可能性を排除できない。これでは、UPBのマネジメントを改善するためには片手落ちである。そのため、本研究では他の非倫理的行動および向組織行動と比較し、UPBにのみ選択的に影響を与える、あるいはUPBには選択的に影響を与えない要因を明らかにすることを目指していた。
2つ目の特色は、UPB概念について単に海外研究の測定尺度を翻訳して用いるのではなく、本邦独自のUPBの構成要素や業界特有のUPBの形態を反映した、本邦の文脈に対応したUPBの測定尺度の作成を目指す点である。不正行為の背後にある道徳心や倫理観は言うまでもなく業界の慣例や組織文化、職場の風土から影響を受ける。このため、日本におけるUPBを海外で作成された尺度で測定することには限界があると考えられる。したがって、本研究では日本におけるUPB研究の先駆として、この限界に対処する。具体的には日本での調査における海外尺度の妥当性を分析し、将来的にはインタビュー調査等を通じた実態調査につなげていく。
上記の目的を達成するため、本助成は質問票調査の実行費用に充てられた。具体的には、インターネット調査会社のモニターを対象に2024年夏に2時点のインターネット調査を行い、先行研究からの予測に基づき、向組織的非倫理的行動に先行する要因を実証的に検証した。この際、海外研究と国内研究の文脈的齟齬を低減するため、質問票の内容は翻訳のチェックをかけた。調査対象は様々な業界の日本企業に勤める従業員であり、最終的に500名の回答から分析サンプルを構築した。
以下、研究の成果として得られた主要な発見事実を整理する。2025年4月現在についてこれらの発見事実の全てが公表成果となっているわけではないが、今後の研究において論文化・公表を目指していく。
①日本の職場文脈におけるUPBの実態
UPBについては海外研究で実証的知見が蓄積されている一方、日本における実証的検討はまだほとんど行われていない。その点において本研究は日本におけるUPB調査の嚆矢である。紙幅の都合上詳細の結果の報告については省略するが、今回の調査では、日本の幅広い業界・組織において実際にUPBが行われているということが示唆された。また、米国をはじめ海外研究では「組織のために『やらなくてもよいことをやる』」行動が典型的なUPBとして俎上に挙げられているのに対し、本国の組織従業員は「組織のために『やるべきことをやらない』」行動を行う傾向があることが示唆された。この結果は今後インタビュー調査等を通じてより精緻に検討していく。
②「組織のために『あえて』不正行為を行う」新たな動機
今回の調査結果からは、日本企業の従業員が「仕事の有意味感を回復するために」UPBを行っている可能性が示唆された。論理的に考えれば、従業員が組織のために貢献する方法は不正行為である必要はない。それでもあえて不正行為を選択する理由は何か。その理由として本研究では「公式的な仕事役割における有意味感の喪失」に着目した。すなわち、従業員は通常の仕事の範囲で仕事に取り組む意味を見出すことができず、なおかつ組織からも離脱できないために、通常の仕事範囲を逸脱してでも組織に貢献し、仕事に取り組む意味を回復しようとする。この結果としてUPBが生じる。今回の調査結果はこのようなUPB独自の発生メカニズムを支持するものであった。
③組織からの職場成果プレッシャーと当事者意識の相互作用によるUPBの動機づけ効果
今回の調査結果からは、日本企業の従業員が組織からの高い職場成果プレッシャーと職場レベルでの成果に対する強い当事者意識の相互作用によってUPBを行っている可能性が示唆された。先行研究において、組織からの強い成果プレッシャーがUPBの生起と関連することは既に知られている。しかし、成果プレッシャーが高い状況下において全ての従業員がUPBを行うわけでは当然ない。このため、成果プレッシャーが高い状況においてどのような特徴を持つ従業員がUPBに手を染めてしまうのか、この問題は依然として先行研究における未解決の問題として残されていた。言うまでもなく、成果プレッシャーが個人の行動変容につながるためにはそのプレッシャーを個人が内面化することが必要である。ただ、本調査では、「職場の」成果に対する組織からのプレッシャーと「職場の」成果に対する個人の当事者意識が「個人の」UPBを引き起こすことを支持する分析結果を得た。この発見事実は日本企業におけるUPBが単なる利己的な動機からではなく利他的な動機の好ましくない発露として生じている可能性を示唆している。
結果発表
1.結果発表の時期
本年度中の発表・公表を目指す(②の一部に関しては既に学会報告済み)
2.結果発表の方法
査読付き学術誌への投稿を検討中