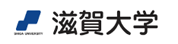一般成人の運動習慣の有無が下肢の伸張―短縮サイクル運動遂行能力に及ぽす影響と運動プログラムの開発
課題1 研究方法
大学生 180 名を対象に連続の鉛直跳躍運動であるリバウンドジャンプテストを用いて 下肢の伸張-短縮サイクル(SSC)運動遂行能力を測定した。
ジャンプ実施時の跳躍高、接地時間、跳躍高を接地時間で除した値であるリバウンドジャンプ指数(RJ・index)を評価項目とした。 さらに1週間当たりの運動回数と時間、運動の種類、スポーツ歴の聞き取り調査を実施した。
課題 1 研究成果
スプリント走と跳躍運動の頻度が高いスポーツ種目を日常的に実施している者や中学、高校在籍時にそのようなスポーツ種目の部活動やクラブチームで活動していた対象者は高いRJ・indexを示した。 また接地時間は、ランニングやスプリント走の量(距離や頻度)の多いスポーツ 種目の実施者や経験者、体重が軽い対象者は短く、跳躍運動の多いスポーツ種目の実施者や経験者の跳躍高は高い傾向にあった。 しかし、SSC運動を伴わないスポーツ種目の実施者やそれらスポーツ種目の経験が短い(無い)対象者、体重の重い対象者は低いRJ・indexと長い接地時間を示す傾向にあった。 これらのことから、下肢における瞬発的な運動の実施頻度と実施経験がSSC運動遂行能力に影響を及ぼしている可能性がある。 これは、現在に加えて、過去のSSC運動遂行能力に影響する運動学習やトレーニング効果が残留している可能性を示唆するものである。
課題 2 研究方法
大学初年次の学生17名をトレーニング介入群8名(陸上競技部)、非介入群9名(球技系の運動部)として定期的にリバウンドジャンプ測定を実施した。
介入群は、プライオメトリックトレーニングやウエイトトレーニング型の運動によるSSC運動向上プログラムを週2~3回実施した。
SSC運動向上プログラムは、力発揮タイミングと力発揮速度の改善、足関節底屈力と股関節伸展力の向上に焦点を当てた運動を導入した。
例えばミニハードルジャンプ(約60cm間隔で接地した高さ20cmのハードルを連続で跳躍する)や階段跳躍(両脚跳躍によって階段を昇る)を中心としたプライオメトメトリックトレーニング に加えて、脚部における屈曲伸展の切り返しを強調したスクワット運動である。 各種運動の回数やウエイトトレーニングにおける重量は、各対象者の体力や体調に合わせて設定した。
課題 2研究成果
トレーニング介入群と未介入群の両群ともRJ・indexが増加する傾向にあったが、 トレーニング介入群において特に跳躍高の向上が顕著だった一方で、末介入群は接地時間の短縮が顕著で あるが、跳躍高の変化は小さい傾向にあった。このことから、トレーニングによる介入がない場合でも、 定期的な運動によって力を素早く発揮することができるようになる可能性がある。しかし、跳躍高の変化が小さいことは、未介入では発揮可能な力の大きさは改善しなかったことを示唆している。 なお、課題1の結果を考慮すると、本課題の対象者は受験のためスポーツ活動から半年以上離脱していた大学初年次の学生であるものの、 中学、高校時には、スプリント走や跳躍運動の頻度の高い部活動で活動していた運動部活動生である。
よって、定期的な運動習慣や過去の運動経験が少ない者は本研究と異なる傾向を示すことが予測できる。
今後の課題
今回の調査から、まず、接地時間の改善に注目する必要があるという仮説を得た。
接地時間の短縮は力発揮タイミングや素早さが関係しており、移動運動の効率化や転側防止に資すると考えられる。
今後は、運動習慣や経験の少ない人に向けた、運動強度の低いプログラムを考案する必要がある。
結果発表
1. 結果発表の時期
2025 年を予定(追加実験及び論文執筆と投稿, 査読期間を考慮)
2. 結果発表の方法
学術誌(体力科学)に投稿予定