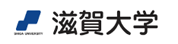史実の発見
歴史研究の醍醐味の一つは、正しいと考えられている学説(史実)を書き改めることにある。そのためには、二つの方法がある。一つは、通説に用いられている周知の史料を新しい分析視角から解釈し、見過ごされた論点を叙述して歴史像を豊かにするやり方である。これはかなり熟練した史料解釈能力と思考の柔軟さが求められる。もう一つは、通説が成立した時点では参照されなかった新しい史料を発掘し、それをもとに書き改める方法である。だれも疑わなかった史実が、たった一つの史料でくつがえったことは、これまでの歴史研究でいくつもの事例はあるのである。この方法は、前者にくらべれば容易なことのように思える。ところが、史実を書き改めることができる史料に出会うことは、一生のうちに一度も経験できない人々がほとんどである。常に問題関心を拡げておく忍耐力がないと、幸運の女神は微笑まないものである。
本年度の企画展は、その意味で女神様の恩寵にあずかったようなものである。ここで出展している史資料は、これまで学界でも未知のものであり、本邦初公開というものがほとんどである。これらの史料群は、たんに近江商人研究を飛躍的に進められることにとどまらず、戦前期日本における商業史、貿易史、商社史などの通説を書き改め、より豊かな歴史を提供できるものである。さらには、総合商社伊藤忠商事・丸紅の前史と戦後の経営史を解明するうえでも貴重な情報が含まれており、現在、斯学界で垂涎の的となっているものである。それゆえ、これらの史資料群を当史料館にお預けいただいた伊藤忠兵衛家・長兵衛家・丸紅株式会社・伊藤忠商事株式会社のご好意には、深甚の感謝の念を持たなければならない。
(附属史料館長 宇佐美英機)
ばっくとぅざぱすと その35
韓国全州歴史博物館を訪うの記

伊藤長兵衛家は、総合商社伊藤忠商事・丸紅の創業家でもある伊藤忠兵衛家の本家であり、当史料館には8,000点を超える史資料が所蔵されている。長兵衛家は、大正十年(1921)に(株)伊藤忠商店と合併し(株)丸紅商店となるまでは、博多・京都・大阪で呉服・太物・洋反物を取り扱う伊藤長兵衛商店を経営していた。明治40年(1907)に韓国全羅北道全州郡参礼面の未開地を購入し、農場経営に乗り出した。この伊藤農場は、丸紅商店が発足した際も、長兵衛家の個人事業として維持され、昭和10年(1935)に伊藤長合資会社に譲渡された。同社は長兵衛家同族の資産管理会社であったが、敗戦によって農場は接収され、長兵衛家同族の資産としては消滅した。
史料館が所蔵する長兵衛家の文書には、この農場に関するものが存在せず、不思議に思っていたところ、昨年、あらたな史料群が発見され、その中にごく少数ではあるが農場関係の史料が伝来していることがわかった。また、以前に韓国から調査に来館した全北大学校の院生から、全州歴史博物館に伊藤農場の史料が所蔵されているとの情報も得ていたことから、今夏、科学研究費助成金を利用して渡韓、調査を実施した。
全州歴史博物館が所在する全羅北道全北市までは、仁川国際空港から高速バスを利用して四時間ほどかかるため、9月2日の夜9時にホテルに投宿する羽目となった。翌朝、歴史博物館を訪問し李東熙館長以下、スタッフに訪問調査の趣旨を改めて説明し、史料目録を作成したいこと、できればデジタルカメラ撮影したい旨を伝えた。幸い、当方の希望はすべて聞き入れられ3日と5日に作業を実施することができた。館長以下学芸員の方々も全員李さんであることには、いささか面食らってしまった。また、その夜には韓屋村にある両班料理店で大歓待を受けることとなったのは、意想外のことで恐縮至極であった。
さらに、4日は晴天になったため参礼面の農場見学をすることになった。私たちは当初、5日にタクシーで出かけることにしていたが、かつて彦根まで訪ねてくれた崔宇中氏と学芸員の李珍成氏がわざわざ自家用車を提供し、参礼面の農場跡地を案内して下さった。これはとてもありがたかった。私たちだけでは、とても跡地にたどり着けたとは思えなかった。農場は見事な水田であり、圃場整備も綺麗にされていた。かつては洪水に見舞われた地に築堤したのも伊藤家をはじめとする、当時の日本人農場主たちであったが、その景観も心に残るものであった。
肝心の史料は、5日も午前9時から午後6時までの開館時間一杯を利用して目録作成と撮影を並行して実施した。結果的に一部の史料については未撮影のままであり、撮影キットを持参せずに撮影した関係で露出やピントに問題がある史料も少なくはないが、目録を完成させるためには十分な状態であった。一日も早く目録を完成させ、そのデータを届けたいと思っている。また、現在はクリアブックに保管されている状態であり、保存方法としては相応しくないため、中性紙封筒や薄用紙を持参して再訪問し、保存方法を改めるように助言したいものだと思っている。
最後に、私たちが今回の調査で一番驚いたことは、あろうことか調査した伊藤農場の史料は、大阪の古書店から購入したものであると教えられたことである。それならば、当史料館が所蔵しているものの分かれではないか、道理8,000点余の中に見当たらなかった筈だと納得した。とはいえ、一部の史料は海を渡ってしまっているが、今後、両国に残された史料を活用して学術研究が進むよう協力しあえる日が訪れることを期待している。
(企業経営学科 宇佐美英機)