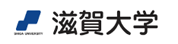アイデンティティーを確立する
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。今年の彦根は例年になく寒さが残る春でしたが、彦根城壕端の桜花は変わることなく皆さんの入学を祝福するがごとく咲き誇りました。
ここで過ごす四年間は、良き社会人として飛翔するための修行・稽古の期間なのです。それゆえ、心して学業・課外活動に励んでもらいたいと切望しています。
ところで、先日、ある企業の新入社員研修でお話する機会を得ました。その場で、社員の皆さんに会社の歴史が記された社史に目を通した人に挙手を求めました。ところが、一人も社史を読んだ人はいませんでした。これにはびっくり仰天しました。自分が社会人として生きていこうとする場(会社)の歴史を学ばないで、就職活動をし、入社したということになります。この実態は、採用にあたった人事担当者も想定外のようでした。
企業が競争優位に立つために、長い年月と努力をかけて社会に認めてもらって初めて、コーポレートアイデンティティーを確立することができるのです。もちろん企業が存続して行く上では、常にイノベーションが必要です。新しい会社の歴史を創造することは、重要な営みです。しかし、それは長い年月の間の先人たちの努力の成果を前提にしていることを忘れてはいけません。
本学部も90年間の星霜を経る中で、世界に羽ばたく知識と行動力をもった人物を養成し、もって社会に貢献しようとする精神を醸成してきました。そのために、人文科学・社会科学の知識を教授することを大切にしています。両科学の分野は、自然科学とは異なり、正解は一つであるとは限らないと教えています。これから経験するであろうさまざまな問題には、たった一つの解しかないのではありません。複眼的に見るならば、多数・多様な解が存在するのです。
たとえば、歴史を学ぶことは、人類が経験したさまざまな事象を知り、現代の諸問題を解決するためのヒントを得ることが第一義ですから、歴史から複数の判断基準を学ぶことが自らのアイデンティティーの確立に役立つことでしょう。創造力は歴史への想像力から生まれ育ちます。そのためにも史料館を活用しながら学生生活を送ってもらうことを願います。
(附属史料館長 宇佐美英機)
ばっくとぅざぱすと その34
シンガポールに現存する最古の団地―ティオンバル団地

シンガポールは、人口の82%がHDB(Housing and Development Board=住宅開発庁)という団地当局の下にある団地に暮らし、しかも人口の80%が、99年のリースという形で分譲団地の一戸を買っています。つまり大多数のシンガポール人が、団地の一戸を買ってそこに住まなければならないのです。私は、このような社会を「総団地化社会」と名付け、現地資料をもとに社会学研究を行っています。
シンガポールの団地は既に相応の歴史を有しており、政府当局が建設した公共集合住宅を団地とすると、シンガポールで初めて団地が建設されたのは1932年になります。HDBの前身機関で、英国植民地時代に事実上団地当局の役割を担ったSIT(Singapore Improvement Trust=シンガポール改良信託)が、ロロンリマウという旧市内の北縁に建てた一階建ての住宅群です。シンガポールの独立後に取り壊され、現存していません。
シンガポールに現存する最古の団地は、写真(1)(2)で示すティオンバル団地です。SITが1936年から建設を始めた団地で、シンガポール初の本格的な団地と言えます。
築80年近くになるティオンバル団地は、さぞ古くさい団地かと思うかもしれませんが、実際に訪れてみると、古くささを感じることはなく、むしろ優雅さというか気品すら感じられます。各戸の間取りは広くて天井は高く、ゆったりとした風通しのいい造りになっています。
私がシンガポールに住んで研究をしていた1998年から2002年にかけては、団地再開発プログラムの下、古くて素晴らしい団地が次々と取り壊されており、このティオンバル団地もひょっとしたら…と、内心危惧していました。
しかし、それはどうやら杞憂に終わったようで、ティオンバル団地は現在、むしろ流行のスポット、観光スポットの一つになっており、シンガポール政府といえども取り壊せない状態になっています。国土の開発・再開発が徹底的に進められる中、古い建物のほとんどが、取り壊されるか「ヘリテイジ」として観光客向けや文化機関向けにわざとらしく保存されるかの二択になっているシンガポールにおいて、人々がそこに生活しながら生きた形で古い建物のよさを体感できる限られた場所がティオンバル団地であり、このことが人気の背景となっているのではないでしょうか。
シンガポールでは、ガーデンシティの名の下、政府当局がいたるところに大量の木を植えています。しかしそれは、政府当局が植えたものだけではありません。写真(2)で示すように、団地では団地住民自らの手によって各戸の前にも植木鉢が並べられ、大げさに言えば、団地住民との協働で団地の景観が創り出されています。写真(2)をよく見ると、植木鉢と柱の間に隙間が空けられていることが分かるでしょうか。これは、歩く人を邪魔しないようにわざと空けられているのです。こういう空間の重要性については社会学者等がよく指摘しますが、それを何気なく実現している点に、ティオンバル団地の素晴らしさを感じざるを得ません。
ティオンバル団地を実際に訪れてみると、そこに存在するのは、以上取り上げた戦前の団地棟だけではありません。このほかに、SITが戦後に建てた団地棟、HDBが1960年代以降に建てた団地棟、近年の団地再開発で既存の団地棟の一部を取り壊した跡地に、HDBが建てた超高層団地棟があります。このように様々な団地棟が並存していることもまた、ティオンバル団地の歴史を表わしています。
本稿を読んだ方には、シンガポールへ行く機会がありましたら、ぜひティオンバル団地にも足を運んでいただきたいと思います。MRTという電車の東西線に乗ってティオンバル駅で下車し、ティオンバルロードに出て東へ向かって行けば、やがてティオンバル団地が広がっているのを目にすることができます。
(社会システム学科 鍋倉 聰)