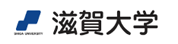伝統に学ぶ
「創り出された伝統」とは、「反復によってある特定の行為の価値や規範を教え込もうとし、必然的に過去からの連続性を暗示する一連の儀礼的ないし象徴的特質」だと喝破したのは、文化人類学者のE・ホブズボウムであった(『創られた伝統』)。
伝統が創出される時、そこには何らかの意図が込められていることに注意することを促している。古くから社会慣習として存在しているからといって、すべてのことが善だとは限らない。伝統のなかに正邪・真偽・善悪などといった対概念を読む時、私たちは慎重な考察が求められる。
本経済学部は、90年前に開学された彦根高等商業学校の伝統を継いでいる。しかし、建学の精神とされる「士魂商才」は、「グローバル スペシャリスト」の養成という言葉に置き換えられてもいる。いずれの言葉も創案された時代における社会の情勢と無縁ではなかった。伝統は、改変されて行くものであるが、通底に流れる思潮は永く生きながらえるのも、また事実である。
彦根高等商業学校校歌は、その第一番で「見よ漫々として琵琶の湖」と歌い出し、第二番では「聞け黙々として語る史書(ふみ)」とした。ここに込められた想いを現代社会で解釈するならば、先人達は早く琵琶湖の環境と歴史の重みを象徴的特質として意識し、学業に励むことを共通規範としていたといえる。
経済学部が21世紀に新しい伝統を創り出すのは、この学窓で過ごす人々の双肩にかかっている。本年度の企画展が、そのきっかけになることを願うものである。
(附属史料館長 宇佐美英機)
ばっくとぅざぱすと その33
彦根高等商業学校からエチオピアへ
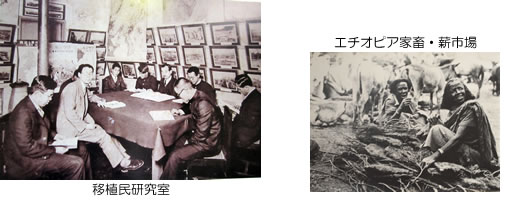
エチオピアと彦根高商とは、なんとも奇異に思われるかもしれません。しかし、史料館に保管されている彦根高等商業学校関係資料のなかにエチオピアの写真がじつに24枚もあるのです。彦根高商調査課に附設された移植民研究室は、植民地事情、海外経済事情等にかんする資料を収集していましたが、そのなかには1940(昭和15)年3月時点で400の写真もあったとされています(「滋賀大学経済経営研究所調査資料室報1―沿革小史―」 『彦根論叢』 第337号、2002年8月、152―153頁)。それら写真のうち、現在、史料館に保管されているのは237枚であり、その多くには彦根高等商業学校の印がおされているか、○のなかに調の字、つまり調査課のシールが貼られ、すべての写真に簡単な説明書きが付されています。その説明書きにしたがって地域ごとに分類すると、そのうちわけは、中国・満州・モンゴル108枚、エチオピアおよびフランス領ジブチ29枚(エチオピア24枚+仏領ジブチ5枚)、オランダ領東インド29枚、南米27枚、北米1枚、ヨーロッパにおける商品見本市13枚、地名記載なし30枚となっています。全体の実に一割を占めるのがエチオピアとその隣接地である仏領ジブチの写真なのです。中国大陸やインドネシア、南米の写真が多くあるのは容易に納得できるでしょうが、エチオピアの写真がこれほど多いことはやはり不思議です。
写真にとどまらず、エチオピアについて学習する機会も多くあったようです。1931(昭和6)年6月17日に、京都大学助教授小牧實繁(のちの第二代滋賀大学学長)を招いて、科外講演「東アフリカ、殊にエテイオピアに就いて」がおこなわれています。小牧はヨーロッパ留学の帰路、摂政タファリ・マコネン(のちのエチオピア皇帝ハイレ・セラシエ一世)に謁見した人物であり、エチオピアに滞在した経験をもつ数少ない日本人の一人でした。また、調査課移植民研究室の支援のもとに生徒が設立した海外事情研究会は、西アジア・東アフリカの綿布市場について実地調査した卒業生を招いて、同年9月に「西亞及び北東阿の綿布市場」と題した講演会兼座談会を催しました。さらに、海外事情研究会の例会において、エチオピアの経済状態について報告した生徒もいました。そもそも最初の例会(1930(昭和5)年7月3日)でも、田中秀作教授が「東アフリカ経済事情、独逸人の海外發展」を演題としています。
彦根高商の人びとが、日本人の移住地があるわけでもないエチオピアにこれほど関心を持った背景には、二つのことが考えられます。まずひとつは、アフリカ唯一の独立国であったエチオピアが親日国家であったことです。エチオピアは、日露戦争に勝利し、国際連盟の常任理事国としてその中核をなした非白人国、日本をその近代化の範に選んだのです。もうひとつは、戦前日本の基幹産業であった繊維産業が目をつけた新しい輸出先のひとつがエチオピアだったことです。1930年ごろのエチオピアにおける輸入の半分余は日本製品であり、その九割が綿布と人絹でした。しかし、それを扱ったのはインド商人であり、ムンバイなどで取引された日本製品が彼らの手を経て、エチオピアに輸出されていたのです。この取引を日本による直接の取引にしようと、1932(昭和7)年にはいくつかの経済事情調査団が派遣されました。その派遣元のひとつが滋賀でした(藤田みどり 『アフリカ「発見」―日本におけるアフリカ像の変遷』 岩波書店、2005年、195頁)。
こうした背景のなかで、彦根高商の人びとはエチオピアへの関心を高め、その地について知ることを欲したのでした。その欲のひとつの現れが、写真の収集だったのでしょう。
(社会システム学科 坂野鉄也)