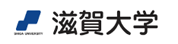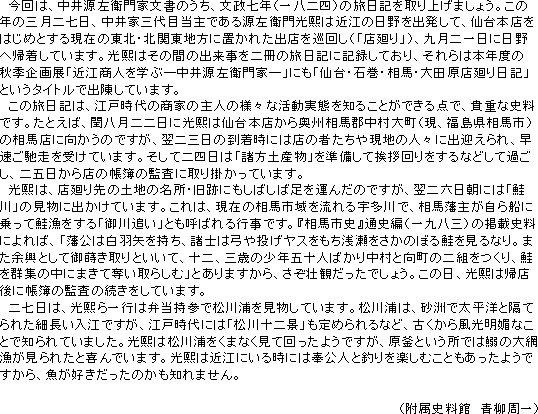次の六〇年を・・・
滋賀大学が六〇年の周年を迎えました。この間、経済学部では附属史料館を中心施設として近江商人・近江地域史の研究・教育に多大な成果を挙げてきました。それは先人たちが県内外に伝来した膨大な史料を調査・収集し、それらを整理し公開に供するとともに、研究・教育に活用するという知的営為の表現でもありました。
それらの中で最大の成果は、蒲生郡日野町大窪に所在した商家である中井源左衛門家の研究です。三万点を超える文書に記された情報は、近江商人の典型を解明するに十分なものでした。しかし同時に、研究で利用された文書は、ごく一部のものであったことも明らかです。
今回の企画展は、近江商人とはどのような商人であったのかを改めて考えてみるきっかけにすべく準備されました。それは、来し方の六〇年の研究を振り返り、次の六〇年にいかに通説を改めていくかということを考える機会にしたいからです。
学問の世界には日進月歩の分野もありますし、何十年の年月でようやく陽の目をみるようなこともあります。しかし、いずれの分野においても根気よく史料や分析材料と地道に向き合い続けるという努力が必要なことは共通しています。歴史的な研究は、それが最も要求される分野の一つだといえます。
十年一日のごとく同じような作業・努力を続けた時に、たった一つの史料や実験から、それまでの通説・常識がひっくり返ったり新発明が生み出されたことは、一度や二度ではありません。これからの六〇年で、近江商人研究も大きく変わることでしょう。それゆえ、斯学の出発点となった中井家を改めて学び直すのは、大きな意義があるのです。
(史料館長 宇佐美英機)
ばっくとぅざぱすと その二十五
出世払いと近代法 (二)

出世払いについて、法律の専門的な議論に立ち入ってしまいましたが、もう少し説明を続けます。
前回は、出世払い約定を停止条件ではなく不確定期限として扱うというのが裁判所の解釈であり、この解釈の根拠は当事者の意思に求められると述べました。とすれば、当事者の意思如何で他の解釈も可能です。例えば、少々特殊ですが、男女のパトロン的関係の下で男性から女性に支払われた出世払い的な援助金を「援助の成功不成功を条件として貸金となるか贈与となるかの条件附給付金である」とした事例も存在します(仙台高判昭26・12・7下民集2巻12号1416頁)。出世払い債務はそもそも債権者が請求力・執行力を持たない一種の自然債務であって、出世が実現したときにだけ訴求可能になると説明することも可能でしょう。
しかし、公表されている裁判例を見る限りでは、不確定期限という解釈は定着しているように思われます。最近の裁判例では、養親が養子に事業資金を貸付ける際に、事業が「軌道に乗ったときに返す」との約束をした場合に、これが期限であること自体はもはや主要な論点ではありません(東京地判平8・10・31判タ926・182)。この傾向は、債権者債務者双方が出世払いを期限ではなく停止条件であると認識している場合には、債務者が出世しなかった場合にそもそも債権者は取立てを諦めるので、我々が容易に観察可能な裁判という舞台に上がってこないからでもあるでしょう。
いずれにしても、出世払いという遅くとも江戸期から日本に存在した仕組みは、明治以降に継受された近代法の枠組の中で、一応はうまく位置づけられたようにみえます。しかし、その際に措定された「当事者の意思」は、果たして当時の現実の市民の意識を反映していたのでしょうか。疑問は残ります。
例えば、先の掲げた現実の出世証文―明治から時代は遡りますが―では、どのようなことが意図されていたのでしょう。出世が実現した場合に債権者側からの取立ては行われたのでしょうか。債務者の自主的な弁済に任されていたのでしょうか。出世が実現せず、弁済ができない場合に、宇佐美教授の説明するような名誉・信用の失墜、あるいは商いの世界からの実質的な退場強制はあったとして、それ以上のサンクションが働いたのでしょうか。明治以降の裁判例のいうように、出世が実現しない場合には繰り延べの約束が失効して債権者による取立てが可能になったのでしょうか。「証人」の役割はどのようなものだったのでしょうか。当事者が親子か商店主・奉公人か単なる知人かといった社会的な関係の濃淡によって、出世証文の扱いに違いはあったのでしょうか。
出世証文自体から、あるいは関連する他の史料、例えば関係者の日記や帳簿などから、こうした点がより明らかになるとすれば、右の疑問に対する解答が得られるかもしれません。
むろん、そうした研究を通じて、仮に明治・大正期の裁判所の判断は当時の市民の意識を反映していなかったという結論になったとしても、法律の世界ではそれだけで出世払いを不確定期限とみる議論が現代において全く立脚点を失ってしまうわけではありません。「出世払いを不確定期限とみるのが当事者の意思に沿う」という説明がたとえ出発点において誤っていても、時間の経過の中でその説明が法律の世界において定着してしまえば以降はそれこそが当事者の意思とされるべきデフォルト・ルールとなるので、明治・大正の出発点あるいはそれ以前に立ち返って「いや、当事者の意思は異なっていたのだ」と主張してもそれだけでは有効な反論にはならないからです。
しかし、法律学にとって、歴史的な事実(特に近代法より前の)を参照することは、近代法の下で主流となった法解釈や意思解釈を相対化して見つめなおし、議論の幅を広げる有効な手段の一つであることは疑いないように思えます。また、日本法の歴史そのものの問題、すなわち継受法と市民の意識の間の乖離が存在したのか、どの程度存在したのか、それがその後どのように埋められたのか埋められていないのかといった問題を考える上で、さらには日本人の法意識・契約意識という一大問題を考える上で、手がかりを与えてくれることにもなるでしょう。
(社会システム学科 須永知彦)