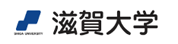築城四百年の中の彦根の近代
今年は、国宝彦根城が築城されて400年目を迎え、彦根市では様々なイベントが企画されています。しかし、「彦根は桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されて以降すっかり沈滞し、明治維新以後も政府に白眼視されてずっと停滞してきたんだ」という近代彦根沈滞論とでも言う歴史観によく出合うことがあります。しかし事実は逆で、直弼以後彦根は見事に近代都市へと発展をとげていくのです。まず、直弼横死以後、政敵であった水戸藩出身の一橋慶喜が将軍に就き尊皇攘夷派が勢力を盛り返すと、彦根藩でも長野主膳や宇津木六之丞らかつての直弼の側近が処刑されて勤皇派が実権を握ります。さらに1867年10月以降、大政奉還によって朝廷を頭に外様大名らも取り込んでふたたび幕府中心の政治再編を目指す動きと、王政復古し幕府を打倒して中央集権的な国家を樹立しようとする薩長などの路線が対立すると、彦根藩は激論の末、下級武士たちが主導権を握って倒幕派に与することに決定します。幕府の譜代大名の雄で、西国大名を監視する役目を担い、かつて安政の大獄で多くの勤皇の志士達を弾圧した彦根藩が倒幕派に転回したことは、幕府倒壊に決定的な影響を及ぼしたと思われます。
その後彦根藩は、鳥羽伏見の戦いから戊辰戦争に至るまで果敢に幕府諸藩と戦って戦功を立て、その過程で薩長の指導者たちとも緊密な信頼関係を培ってゆきます。廃城令が出され多くの城が取り壊されていった中で、彦根城が解体を免れて残されたことも政府高官との密接な信頼関係の賜物でした。その後彦根は、大久保利通や大隈重信ら政府指導者と緊密な協力関係を維持しながら、県営彦根製糸場を開場して周辺地域を一大蚕糸業地帯に発展させたり、また現在の滋賀銀行の前身である第百三十三国立銀行を創設して金融面での支援体制を整え、近江鉄道を開設し、バルブ産業や仏壇産業を勃興・発展させたりして、みごとに近代都市へと脱皮していくのです。その延長線上に、大正期の近江絹糸会社の創業があり、国立の高等商業学校の彦根への誘致が実現されていくのです。
築城四百年祭では、こうした彦根の近代化過程にも光が当てられていますが、史料館の春季企画展でも彦根の近代商業の生き証人である「引札」を多数展示しています。ぜひ多くの方に、魅力ある彦根の近代史のひとコマに触れていただきたいと思います。
(史料館長 筒井 正夫)
ばっくとぅざぱすと その二十
芝棟との出遭い(一)
 「芝棟(しばむね)」に私が出遭ったのは、しばらく前から興味をもって読んでいた徳冨蘆花の作品『自然と人生』のなかでだった。ただ、そのときは、まだそれと知らぬ出遭いだった。そこに収められた「自然の色」という小品において蘆花は、彼が愛した上州を旅したときのことを次のように記している。「伊香保を出でける頃ほと?傘を敲ける雨は澁川に到りて止み、水濁れる利根を渡りて前橋の方に半里も行く程に、雲は北へ北へと捲き去りて、午日の光雨の如く降り來ぬ。・・・此あたり人家の屋根には概ね菖蒲を植へたるが、折しも五月初旬の事なれば、濃き薄き紫の花淺?の葉まじりに蔟(ぞく)々と咲き出で、茅舎(かやゝ)も花簪(かざ)して立つ思あり。」このときには、人家の屋根の上に菖蒲が植えられていて花が咲いているのかと、ただそう思った。せいぜい、世の中には変わったことをする人たちがいるものだという気持を抱いただけだった。
「芝棟(しばむね)」に私が出遭ったのは、しばらく前から興味をもって読んでいた徳冨蘆花の作品『自然と人生』のなかでだった。ただ、そのときは、まだそれと知らぬ出遭いだった。そこに収められた「自然の色」という小品において蘆花は、彼が愛した上州を旅したときのことを次のように記している。「伊香保を出でける頃ほと?傘を敲ける雨は澁川に到りて止み、水濁れる利根を渡りて前橋の方に半里も行く程に、雲は北へ北へと捲き去りて、午日の光雨の如く降り來ぬ。・・・此あたり人家の屋根には概ね菖蒲を植へたるが、折しも五月初旬の事なれば、濃き薄き紫の花淺?の葉まじりに蔟(ぞく)々と咲き出で、茅舎(かやゝ)も花簪(かざ)して立つ思あり。」このときには、人家の屋根の上に菖蒲が植えられていて花が咲いているのかと、ただそう思った。せいぜい、世の中には変わったことをする人たちがいるものだという気持を抱いただけだった。しかし、これが別に「変わったこと」ではなく、時代を少し遡れば日本の随所で見られた珍しくない風景であることを知ったのは、幕末に来日したプラントハンターであるロバート・フォーチュンの『幕末日本探訪記』を読んでいたときだった。フォーチュンは神奈川の農家の前を通り過ぎたとき、その茅葺の屋根を見上げた。すると「屋根の背に、ほとんど例外なく、イチハツ(注)が生えていた」。さらに、その文に付されたイラストを見ると、そこには、屋根の棟の上に植えられて、ふさふさと葉を茂らせている植物が描かれていたのだった(図1)。 その絵を見て初めて私は芝棟というものを理解したのである。〔注 : イチハツと菖蒲はよく似た植物であり、蘆花が上州で見た植物はおそらくイチハツだったと考えられる。〕
それ以来芝棟についていろいろ調べてみたところ、むかし日本では茅葺屋根の棟に通常は芝土を乗せ、あるいはさらにイチハツなどの植物をそこに植える風習があったことがわかった。土地によってはユリやイワヒバなどを植えたという。薄褐色の茅葺屋根の上に紫色のイチハツや朱色のユリの花が咲いている光景はなかなか美しかっただろうが、芝棟は本来、審美目的のために作られたのではなく、茅葺屋根で最も弱い部分である棟を強化するために工夫されたものであるという。芝土を乗せることによって棟がしっかりと固められ、さらにイチハツやユリの類いをそこに植えることによって、よく張る根で土を固定し、棟を頑丈なものに仕上げていたのであるした史料館所蔵史料のなかの、興味深い事例の一つを紹介しておこう。
その後、亘理俊次氏が『芝棟 屋根の花園を訪ねて』(八坂書房 1991年)という、芝棟を総合的に研究された本を著しているのを知った。それを読むと、芝棟は「古い時代から民家建築に普通な草葺屋根の棟の一形式で、植物を植え、根を張らせて棟の固めとする手法の総称」という説明がなされていた。屋根を茅などで葺くのが普通だった時代には日本各地で普通に見られた風景であって、ことに横浜周辺、また群馬・長野をはじめとする関東甲信地方、さらに東北地方の民家で多く見られたという。しかし第二次大戦後、そして高度経済成長期を経て、日本で茅葺屋根の家が減少していくとともに、芝棟も急激に姿を消していったとされる。
日本全国を旅した民俗学者の宮本常一氏も、鉄道路線でいえば中央線や常磐線沿いで、芝土を乗せた屋根にたびたび出遭い、北は岩手・青森から南は阿蘇山の東などでも芝棟を眼にしたと述べている(『日本の村・海をひらいた人々』ちくま文庫)。
芝棟のことを知ってからというもの、私は昔の茅葺屋根を撮影した写真や茅葺の民家を描いた絵を見ると、芝棟になっていないかどうか、まず確かめようとする癖がついてしまった。そして、たいそう有名な絵のなかに芝棟が描きこまれているのを数多く発見したのである。 〈以下、次号に続く〉
(社会システム学科 金子 孝吉)
史 料 紹 介
奥野文雄家文書について
 諸願出届出留(奥野文雄家文書)
諸願出届出留(奥野文雄家文書)今回ご紹介する奥野家文書は、彦根市本町の奥野文雄氏から史料館に寄託された史料群です。同家は江戸時代には上魚屋町(現、本町2~3丁目)に居を構えて、「郷宿(ごうやど)」という特殊な仕事に従事していました。
「郷宿」とはなじみのない言葉でしょうが、『国史大辞典』を引いてみますと、「江戸時代、城下町や陣屋など藩庁・代官所所在地に滞在する領民の定宿。郷宿の数は各地でほぼ一定しており、主に公用の大庄屋・庄屋などを顧客とし、訴訟などに出るものも宿泊した」と説明されています。つまり、大名が治めていた藩を例にしてみますと、藩領内の村々に住んでいた人々が訴訟を起こしたり、裁判を受けたりする場合には、藩の政治の中心地である城下町にいちいち出てこなければなりませんでした。そうした人々に対して、城下町での宿泊や訴訟手続きの世話などを行なっていたのが、郷宿だったのです。
奥野家文書には、彦根藩の村々が関わった争論についての文書が数多く含まれており、同家が彦根藩の郷宿として、それら村々による訴訟や裁判に深く関与していたことが明らかです。なお『彦根市史』に、「郷宿は多くは奉行所の近くにあって、一般の客を宿泊せしめなかった。(中略)下魚屋町(宮村・西村氏)職人町(遠藤氏)上魚屋町(奥野氏)本町(疋田氏)元川町(伊藤氏)四十九町(中村氏)などがその例である」と記されているように、彦根には奥野家ほか六軒の郷宿があったようです。
江戸時代の地方城下町での郷宿の実態は、現在まで必ずしも具体的には明らかになっておらず、この点でも奥野家文書はまとまった郷宿の史料群として、研究上高い価値があります。また同家文書中の数々の訴訟関係史料は、それら訴訟に関わった彦根藩の村々の歴史の研究に役立つものであり、さらに訴訟・裁判の際に藩と村々を仲介する立場にあった同家について研究することは、彦根藩の行政のしくみを明らかにする上でも大きな意味があると言えるでしょう。
史料館では今回の春季展示に引き続き、秋にも国宝・彦根城築城四〇〇年祭の後援事業として彦根の歴史を特集した企画展を開催しますが、そこでは奥野家文書の一部も出陳する予定です。
(附属史料館 青柳周一)