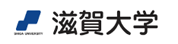青柳周一(本学経済学部教授)
2020年度のわたしたちのワークショップは、COVID-19にかかわる制約のもとでの実施が見込まれ、それゆえに、距(へだた)り離れざるを得ないなかで、そのうえでなお、「共に」、との意図をくわえた、ReD # ensembleを名称とした。その第1回をようやく、7月18日(土)に、Zoomミーティングによる青柳周一さんの報告として組むことができた。論題は、「沖縄から内地へ向かう修学旅行の歴史:戦争・差別・史料」。
青柳さんは、去年2019年に刊行された、桂島宣弘ほか編『東アジア 遭遇する知と日本:トランスナショナルな思想史の試み』(文理閣)に、「近代沖縄の内地修学旅行記録を読む:一九一〇年『三府十六県巡覧記』について」と題した稿を寄せている。そこにいう史料は、「沖縄県師範学校の生徒だった前原信明による、1ヶ月以上に及ぶ内地修学旅行」の記録で、今回の報告はそれ以前の、「沖縄で最初の内地修学旅行」である1893年の尋常師範学校による「九州への修学旅行」をとりあげた。本報告では、生徒の修学旅行としての沖縄から「内地」への往復移動と、そしてもうひとつ、昨年刊行編著に収載された稿で活用した史料の同様の移動との双方を論じるとの姿勢が、本報告副題の「史料」の語に籠められていた。
本報告の論点はひとつに、巡覧記であれ旅行記録であれ、そうした史料(テキスト)をどう読むか、にあった。レジュメにもあった、「「南門」観と共に、自らに課せられた教育方針を深く内面化した」ということと、旅行先での「差別される恐怖感」や「沖縄への帰還と「安堵ノ心」」とをどうつなげた歴史を、史料解読者が記述するのか、また、そう記されたり記されなかったりした史料から、当事者の「体験」をどのように再構成したり論述したりするのか、さらには、旅行をしなかった「沖縄人」たちの「体験」(あるいはこれは、無体験や未体験となるか)を、その再構成や論述に籠めるのかどうか、ということだ。
青柳さんの前掲論文には、『三府十六県巡覧記』にみえる「夢より醒まされたる身は、覚めたまゝ暗黒の裡に葬られたこと」との文言が引用されている。このように書き記され、いまにのこる史料から当時の人びとの「体験」を表現する言葉を、わたしたちは粘り強く練る技量を身につける必要がある。報告で言及のあった鹿野政直は、「伊波普猷とその時代」と副題をつけた著書の書名を「沖縄の淵」とした。鹿野ならではの、表現である。
青柳さんは、その展望を「構造」をとらえるところに見晴るかそうとしているようだった。ディスカッションでは、充分には展開させることができなかった、「国家と旅行」という観点や論点、報告副題にいう「差別」もまた、その「構造」の把握につながるだろう。
当日は、午前中に「学術情報ネットワーク」の「機器故障」が突然おこり、Zoomミーティングの利用が危ぶまれたが、遅滞なくワークショップは、実施、完了した。「オンライン講義は無限大の教育の可能性を開いたことになります」と手放しの称讃を「きらきら」と歌いあげられるものは、こうした奇禍(アクシデント)がおこらないよう、みずから日々の装備点検を、きちんと、しておくとよい。
( 阿部安成 )