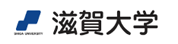小野文生(同志社大学准教授)
今年度第2回目のマンガ学ワークショップIIが2019年2月21日(木)に開催された。講師に小野文生氏(同志社大学准教授)をお招きし、2015年に没した哲学者・鶴見俊輔の漫画論を出発点として、哲学や思想、市民運動の方法論にまで至る鶴見の多様な側面にまつわるお話を伺った。
満鉄初代総裁・後藤新平の孫として政治家の家系に育った鶴見は、母親との関係に苦しんで「不良」となり、逃げ出すようにアメリカに渡る。渡米した鶴見は、日本語を忘れてしまうほどの猛勉強で英語をマスターし、カルナップやクワインといった第一級の哲学者の教えを受け、プラグマティズムを日本に導入した立役者となった。日本語が自身の執筆言語として確立されるまえに渡米したために、帰国後の鶴見は反対に日本語を「学び直す」ことになる。その過程で、若いころには国語辞典を使って書かれていた鶴見の硬質な日本語は、次第におしゃべりをしているかのような自由闊達な文体へと変化していく。小野氏によれば、鶴見の試みとは言語を変えることで思想を変えることだった。そのとき、つねに鶴見の参照点だったのは、子ども時代に愛読した宮尾しげを『団子串助漫遊記』に端を発する一連の漫画作品である。現在とは異なり、大人が当たり前に漫画を読むわけではなかった時代に、漫画は、小野氏のまとめを借りれば、娯楽/遊びとして、解放/自由の契機として、抵抗/反逆の手段として、知識人/文化の批判として、日本社会を映し出す鏡として、さらには哲学の根として、鶴見の思想と切っても切り離せない役割を担い続けた。
実際、個々の漫画論には、そのつど鶴見の思想とも交差する視点が現れる。『団子串助』が用いる「おとなとの対立をやわらげ、無理せずに目的を達する」方法は鶴見のアナキズムの具体的方針を描いていると言えるし、同じ宮尾の『一休さアんと珍助 漫画と漫文』に現れる、竹刀にも「竹刀の道があるはずだという悟り」は、イミテーション(模倣)に創造的な営みを見て取る鶴見の立場とも通じている。まじめさ・純粋さ・権威といったものがもつ避けがたい暴力性にあらがって、「自分のたましいの故郷」は「浅いところにある」と言う鶴見は、不純なもの・混ざりあったもの・薄っぺらいものに「理想」を見いだす。ただしこの「理想」は、不純で混ざり合っていて薄っぺらいものである以上、あくまで「理想を高くかかげたくないという理想」でもある。こうした鶴見の姿勢には、運動の方法論としては脆弱だという批判が向けられたこともあったが、だからこそこの「理想」は、みずからの誤謬可能性をうちに含んだ運動の原理として、ひとつの理念や主義に固着しない「ユートピア」を指差すものである。この「マチガイ主義」、自分の限界の認識に根ざしたunlearn(学び直し・学びほぐし・学び捨て)の態度こそが、鶴見が漫画という浅いところから引き出してくる批判的精神だった。
鶴見は、普通のひとびとが普通にできることを通して社会を変えようとし、新たな倫理を立ち上げようとした。しかし、この倫理とは一体なにか。漫画は「民衆の自画像」であると考えた鶴見は、山上たつひこの『がきデカ』をこよなく愛した。金とセックスだけを追い求める人間が活躍する『がきデカ』が日本中で読まれることで、そうした人間像が「暮らしの中の反射」として子どもたち、大人たちのなかに育まれていく。このダメな自画像を通して自分の姿を学び取ることが、みずからの正しさを疑うことなく大上段に構える倫理とは異なったエートスをもたらすのだ。だが、ワークショップの参加者からの鋭い指摘にあったように、こうした「反射」はともすれば反射的な排除を生み出し、いつしかそれが巨大なシステムと化してしまうおそれもある。自分の足元の暮らしに根ざしつつ、それでいて異なる他者への想像力の余地を残すような暮らしの叡智――いま鶴見を読み直すことは、こうしたユートピア的なトポスを探る手がかりになるように思える。
筆者の大学生時代には、蓮實重彦や柄谷行人、浅田彰といった綺羅星のごとき批評家たちが聖書のように読まれ、しかも東浩紀という新しいタイプの批評家すらも現れるに至って、鶴見や小田実らの世代の思想は影に隠れていた感があった。しかし、今回のワークショップで接した鶴見の文章からは、自分の過去の不明を恥じるほどの大きな刺激を受けた。個人的な思い出も交えて鶴見のテクストを精緻に紹介し、鶴見の思想との出会い直しのきっかけを与えてくださった小野氏に、あらためて心から感謝したい。
(文責 藤岡俊博)