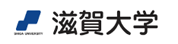企業成長持続のための事業ポートフォリオ・マネジメントの研究
本研究は、日本企業の活性化のマネジメントへ向けて、日本企業の経営の今後のあり方についての洞察を得ることを目的として、企業が長期成長するためのマネジメントのあり方を探る探索的研究である。より具体的には、過去の経営学の研究などの成果も踏まえて、企業が長期存続するためには、企業成長には事業ポートフォリオを健全な状態に維持し続けるマネジメントが鍵となるという観点から、事例収集や理論的な考察を図ることが本研究の目的であった。そこから、科学研究費などによる大規模なアンケート調査を行う上での、質問項目や理論的な分析フレームワークを探ることも意図されていた。
本研究では、事業開発(多角化)や戦略計画などの経営学の研究にあわせて、政治と権力などについての哲学の分野を含む領域の文献研究を中心とした。哲学の文献は、事業開発やそれをリードする経営者の意志や自我のあり方も重要な分析の要因となりうると考えたためである。
研究のアウトプットとしては、2017年12月に刊行された共著『100年成長企業のマネジメント』(日本経済新聞社)に若干の追記を加える際に本研究の成果を加味している。より本格的には、本年度以降の論文執筆に研究成果を反映させる予定である。
本研究の成果として、次のような洞察に到達した。
企業が長期的に成長を持続するためには、そもそもの研究目的として提示したように、究極的には、事業ポートフォリを更新し続ける必要がある。どのような事業にもライフサイクルがあり、事業そのものは盛衰する。事業の盛衰と企業の盛衰を切り離すためには、企業は複数の事業をもち、常に、衰退しつつある事業を閉鎖し、成長し利益の確保できる事業を育成するプロセスを継続しなければならない。このような事業ポートフォリオのマネジメントのあり方自体は、以上のような事業のライフサイクル論から引き出される論理的な必然である。
しかし、現実にそのような事業ポートフォリオのマネジメントを継続的に実行できる企業は例外的な存在である。また、アメリカ企業と比較した場合、一般的に、日本企業はこのようなタイプのマネジメントを苦手とすることも指摘されている。近年、アメリカ企業と比較した、日本企業の収益率や企業価値の低さなどが批判され、また、政府等が主導で企業統治改革を進めようとする現下のわが国の企業環境、そして、バブル期以降、成長や成功の方程式が不分明になっている日本企業がどのように事業ポートフォリオ・マネジメントを強化できるのか、また、それはアメリカ企業のそれとどこが共通する点であるのか、また、どこでわが国の独自性を維持する必要があるのかが問われることが必要となる。
まず、事業ポートフォリオのマネジメント力を強化するためには、日本企業においても、アメリカ企業と同様に、ゼネラルマネジメントを担う人材の育成が必要となる。それは、従来の日本企業のジョブローテーションなどを通したジェネラリストの育成とは異なり、若い年齢で事業部長や海外子会社の経営責任者を経験させるなどの、経営幹部の選抜と教育が必要とする。ただし、このような選抜主義は社員全体の長期雇用とは矛盾しない。 また、日本企業の独自性としては、この長期雇用の指摘と関連するが、社員及び経営者の会社へのコミットメントの高さにある。ただし、長期雇用や会社へのコミットメントの高さは、一方で、馴れ合いやグループシンク(集団浅慮)に陥る可能性を高める。事実、バブル期以降の日本企業の競争力の喪失の原因として、これらの特徴は指摘されることがある。しかし、かつてアベグレンが指摘したように、このような会社のあり方は日本独自の会社観を現すものであり、それ自体は日本企業の強みにもなれば、弱みともなるものである。事実、高度経済成長期からバブル期まではこのような会社観がいわゆる日本的経営を支えてきたのである。
以上のような問題意識を踏まえて、現在問われているのは、日本的な会社観を再活性化しながら、そのうえに重ねるようにゼネラルマネジメントの能力を強化し、また、事業ポートフォリオのマネジメントを上手にコントロールする経営上のルールなども取り入れることである。その際、改めて、組織に対する個人の関係性も問い直される。会社は、個人とは別の守り育むべき大事な存在であり、そのためにそこに関わる諸個人は自己を律し、経営に関与することで自己の生を実践するという原理を出発点に、どのような経営学を構築できるのかがそこで問われているのである。徳や倫理などの哲学の概念も重要な洞察を提示する。今後の研究の方向性としては、以上の論理を具体的な質問項目に置き換え、アンケート調査の設計を進めるとともに、日米企業の事例の蓄積を図ることである。
研究成果一覧のページに戻る